第7回年次講演会「食後高血糖とスローカロリー」
特別講演①「インスリン生誕100周年記念 "糖のながれ"を意識して、血糖値スパイクを防ぐ」
●テーマ:「インスリン生誕100周年記念"糖のながれ"を意識して、血糖値スパイクを防ぐ」
●公開:2021年3月21日~

河盛隆造先生
順天堂大学名誉教授、同大学院医学研究科 スポートロジーセンター センター長

トロント大学留学と"糖の流れ"
河盛先生とトロント大学との関係は、先生がインスリン発見からちょうど50年目の1971年に、同大学へ留学した時に始まる。
現地に着いた初日に、インスリン発見者の一人であるベスト先生に面会する機会を得たそうだ。大阪大学で経口インスリンの開発をしていたことをお話しされたところ、ベスト先生は「世界中のウシやブタを集めて貴重なインスリンを生産しているのに、皮下投与の数十倍も必要な経口投与などとんでもない」と叱責されたという。それに対して河盛先生は、インスリンを内因性に門脈経由で供給してこそ生理的な糖代謝制御が可能になるのではないかと応えたところ、ベスト先生は「確かにそうだな」と頷かれたそうだ。
このベスト先生とのやり取りには後日談がある。2カ月後に、トロント大学でインスリン発見50周年の盛大なシンポジウムが開かれた際のことだ。ベスト先生の講演に、若き河盛先生がスライド係を担当された。講演の途中でベスト先生が突然、「インスリンが発見され50年がたつのに、いまだ高血糖で合併症を来す患者が多数いる。医師がインスリン投与量を決められないのであれば、膵移植や人工膵臓の開発を急ぐべきだ。そして経口投与可能なインスリンの開発も期待される」と発言されたそうだ。河盛先生は、「スライド送りをしながら驚くとともに、大変感動したことを鮮明に記憶している」と語っている。
先生は留学中、イヌにアイソトープを用いて糖の分布、糖の流れを繰り返し研究された。そのことが、インスリンとグルカゴン、そしてグルコースというこれら三つのバランスが、いかに血糖の恒常性に重要であるかを明らかにし、かつ身体活動、運動の重要性に関する研究を続けることになられた。トロント大学の経験が、"糖の流れ"をめぐる先生のライフワークの契機となったように伺える。
スポートロジー学の創設
トロント大学より帰国後は、臨床と研究を重ねながら、運動やスポーツにサイエンスを求めて、「スポートロジー」という学問の創設の必要性を実感し、実際にその学問体系を作り、様々な研究を展開されることになった。
さて、現在、普通体重なのに内臓脂肪が蓄積している人、"やせメタボ"が急増している。多くの医師は「食べ過ぎが原因だ」と言う。河盛先生はこの考え方に疑問を投げかける。「本当だろうか? そうではなく、運動不足によりエネルギーを消費しない体質に変化しているのではないか」。そう考えた先生は、それを実証する複数のデータを報告されている。
一方、さらに新しい問題は、若年女性の間で広がっている。若年女性は健診結果で全く異常がなくても、詳しく調べると、ビタミンD欠乏、骨粗鬆症の該当者が極めて高率に存在するのだという。若いサルコペニア"若ペニア"あるいは"若フレイル"だ。先生は「これで日本の将来は大丈夫だろうか?」と憂える。
河盛先生が一貫して「糖の流れ」を研究され、数々の知見を報告してきたことはよく知られている。糖尿病の序章である食後過血糖を改善するには、食事による糖負荷を穏やかにして、肝臓へのブドウ糖流入にできるだけ時間がかけるような工夫が望まれる。そのために、食物繊維の多い食品から食べる、清涼飲料水は飲まない、α-グルコシダーゼ阻害薬を適宜使うといった戦略を提唱されてきたのも河盛先生である。
糖尿病患者数が増加し、専門医が疲弊しかねない状況にある今、先生は「食後過血糖の段階で、糖を緩やかに吸収させるという戦略を、日本中に広げるべき」としている。
コロナ禍の今だからこそ、見直そう
講演の後半では、正に喫緊の課題であるコロナ禍についても言及している。糖尿病患者は重症化リスク化が高い。しかし先生は、「コロナ禍を転じて福となすべきだ」という。具体的には、時間に余裕が生まれたのであれば、食事をゆっくり味わうことでおいしく召し上がれるはずであり、食後に運動をすることもできるはずだと語る。
そして最後に、「我々は力をあわせることで、必ず不可能を可能にすることができる。遠くない将来に、コロナは終息するだろう。その日を待ちつつ、日々の血糖と体調の管理を続けていただきたい」と講演を結んでいる。
●テーマ:「運動とスローカロリー:血糖コントロールの重要性」
●公開:2021年3月21日~

宮下政司先生
早稲田大学スポーツ科学学術院運動代謝学研究室准教授
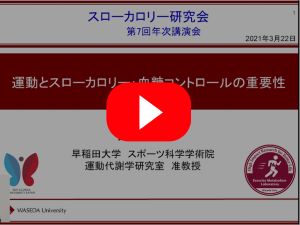
異なるGI食品摂取後の運動時の代謝
宮下先生は、講演冒頭で、運動にグリセミック・インデックス(GI)が低くスローカロリーである「低GI食品」を応用することにより得られる理論上のメリットをリストアップした。
低GI食により摂取後の血糖上昇が抑制され、その後の運動中に適度な血糖レベルが維持されることや、インスリン分泌を過度に刺激しないため運動中脂質分解が抑制されにくく、グリコーゲンの温存につながり、パフォーマンスが向上する可能性を指摘。そのうえで、それらを実証したエビデンスをいくつか取り上げ解説。
例えば、男性アスリートを対象としたクロスオーバー試験では、運動前に低GIの食品を摂取した場合、高GIの食品に比べて運動中の血糖値が高値で維持され、かつ、遊離脂肪酸や呼気ガスで評価した脂質酸化レベルが、低GI食品摂取後の運動時に高値だったという。
これは、高GI食摂取後に比較して運動中の脂質代謝が亢進していることを示していると考えられ、グリコーゲンの温存を表している可能性があるとのこと。この研究では、結果として、低GI食摂取後のほうが、疲労困憊までの時間が延長されていた。
運動後における代謝や食欲との関係
アスリートの体づくりにとって運動後の食欲維持は重要である。トレーニング終了後、できるだけ早く炭水化物、タンパク質を中心とする食事を摂取することが、筋グリコーゲン合成に重要とされる。しかし実際には高強度のトレーニングによって食欲が低下してしまい、十分に食事をとれないアスリートがいるという事実に言及。そのメカニズムとして、消化管の血流減少による機能低下や、食欲刺激ホルモンであるグレリン分泌の低下などの影響が想定される。
これに対し宮下先生の研究グループでは、温かい飲み物を摂取することで胃の収縮が増加し、胃内容の排出が促進されるという先行研究に着目。健常男性を対象に、運動負荷後に冷温、常温、高温(60℃)の飲料を摂取するという3つの条件でのクロスオーバー試験を実施した。
その結果、60℃の飲料を摂取後は他の条件に比較し胃幽門部収縮回数の有意な増加が認められ、さらにビュッフェ形式での自由摂取時の摂食量が有意に増大したという。また、浸透圧の違いも食欲に影響し、浸透圧の低い飲料のほうが胃の活動が亢進し摂取エネルギー量が増えるとのことである。
このほか講演では、運動量が同等であれば一度に行うよりも、何回かに分けて行ったほうが、血糖管理上のメリットが大きい可能性など、スローカロリーの話題を中心としつつ、運動と血糖に関する最新の知見を紹介した。
「運動とスローカロリー:血糖コントロールの重要性」まとめ
宮下先生は、今回の講演である、GI食品摂取後の「運動時の代謝」「運動パフォーマンス」「運動後の代謝と食欲との関係」について、以下のようにまとめた。
- 運動前の低GI食品の摂取により運動時のグルコースが維持され、脂質代謝を 亢進させる。
- 運動前の低GI食品の摂取により運動パフォーマンスの向上が示唆されている。
- 代謝や食欲の観点も考慮しながら、運動後の食事の質(GIの種類)等に留意 することが肝要である。
