糖尿病とスローカロリーを考える

難波光義 先生 (宝塚市立病院 事業管理者、スローカロリー研究会理事)
血糖とインクレチン分泌に及ぼすパラチノースと砂糖の違いに関する研究結果から
パラチノースと砂糖を摂取した後の血糖、インスリン、インクレチン分泌の変化を比較分析する研究が健常人を対象に行われ、パラチノースが砂糖よりも血糖変動やインクレチン分泌において有用性をもつことが明らかになりました。この結果は、平成25年5月に熊本で開催された第56回日本糖尿病学会学術集会で発表されました。
今回、この研究結果を振り返りながら、パラチノース摂取の有用性について、研究リーダーの兵庫医科大学糖尿病・内分泌代謝科主任教授の難波光義先生(現 宝塚市立病院 事業管理者、スローカロリー研究会理事) にうかがいました。
本インタビューは、2014年7月糖尿病ネットワーク「スローカロリー情報ファイル」に掲載されました。(2022年6月スローカロリー研究会に移設)
1. パラチノースの特徴とは?
---- パラチノースの特徴とは?
難波: この結果はパラチノースの構造にヒントがあります。私たちの小腸にはαグルコシダーゼという消化酵素があり、吸収直前になってはじめて単糖に分解されるようにすることで、腸内細菌などに栄養を奪われにくくする働きをしています。
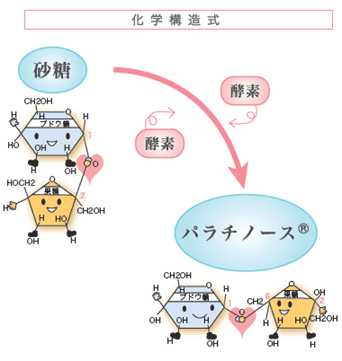
難波: パラチノースは、唾液、胃酸、および膵液の消化作用を受けず、小腸でαグルコシダーゼの一種であるイソマルターゼという酵素によってグルコースとフルクトースに分解され、小腸内ですべて消化吸収されます。この酵素反応はゆっくり進むので、パラチノースの消化吸収速度は遅く、過去の研究によると砂糖の約1/5 と言われています。そのため、摂取した際の血液中へのグルコースの流入が砂糖よりも穏やかで、血糖値やインスリン分泌の急激な変化を引き起こしにくいというのが特徴です。
砂糖を大量に摂ると激しく血糖値が上がり、それに反応してインスリンが過剰に出るので、少し遅れて反応性低血糖が起こります。パラチノースの場合は急激に血糖値が上がらないので、インスリンは穏やかに出て、穏やかに推移します。摂取後の血糖変動の山(ピーク)は低く、谷も穏やかになるということです。これによって、高血糖の悪影響を軽減できるのと、その反動(反応性)による下がりすぎがないので、空腹感を助長することも少なくなるというように、両方を軽減できるのがパラチノースのメリットですね。
砂糖とパラチノース 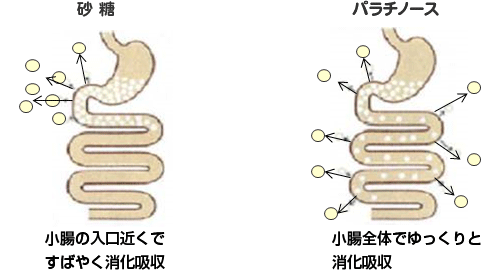
---- 先生は、パラチノースを以前から注目されていたのですか?
難波: 実は、この研究を行う少し前まで、砂糖と同じ二糖類にこういうものがあるのを知らなかったのです。僕たち医者は、食品のことって意外と知らないんですね。食事療法の指導では、カロリーや摂取量のこと、たんぱく質や糖質、脂質といった成分のことについては何となく気を遣うけど、消化吸収過程のことまで考えることがありませんでした。
消化吸収を考えた指導としては、ファイバー。繊維をたっぷり摂ると吸収が穏やかだから、野菜をたっぷり先に食べましょうねとか、よく噛みましょうねという話になるのですが、同じ糖質で、同じカロリーでも消化をゆっくりにするノウハウがあることなんか考えもしなかったんです。ここまで作り上げたお砂糖屋さんの大きな手柄だと思います。
2. 血糖値とインスリン分泌量を比較
---- 研究のはじまり
難波: パラチノースに関する過去の研究からみた作用機序を知り、分解・吸収が穏やかであるということは、今我々が使っている糖尿病治療薬αグルコシダーゼ阻害薬(α-GI)のコンセプトに非常に近いなと直感で思いました。
消化管のホルモンは単糖になってはじめて刺激されて分泌されるということはわかっていました。二糖でもオリゴ糖でも出ない(刺激しない)。ということは、α-GIで単糖になるステップを邪魔すれば小腸上部の消化管ホルモンは出にくくなり、下流に到達したときの単糖が小腸下部の消化管ホルモン分泌を促すことが作業仮説ではわかっています。
消化管ホルモンとして知られるインクレチンには、GIP(グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド)とGLP-1(グルカゴン様ペプチド1)という2種類があります。GIPは小腸上部(主に十二指腸)で、GLP-1は小腸下部(回腸)で多く分泌されるホルモンです。つまり、単糖が小腸のどの部位で消化管ホルモンを刺激するのか?によって、GIPとGLP-1の分泌バランスが変わってくると予想されるわけです。
パラチノースは砂糖よりもゆっくりと消化吸収されるため、消化管下流に到達してはじめて単糖になる成分が多いと考えられ、このα-GIの作用コンセプトに近いなと思ったのです。そこで、パラチノースを飲んで普通のお砂糖の場合とインクレチンの分泌バランスを比べてみたらどうかなというのがこの研究のはじまりです。
---- 結果はどうだったのでしょうか。
難波: 今回はいきなり糖尿病患者さんというわけにはいきませんでしたので、健常者の方を被験者にしました。
図1を見てください。これが砂糖とパラチノースを摂取した際の血糖値の推移です。砂糖と比較してパラチノースの血糖変動は予想通り山(ピーク)は低くなり、谷は浅くなりました。
図1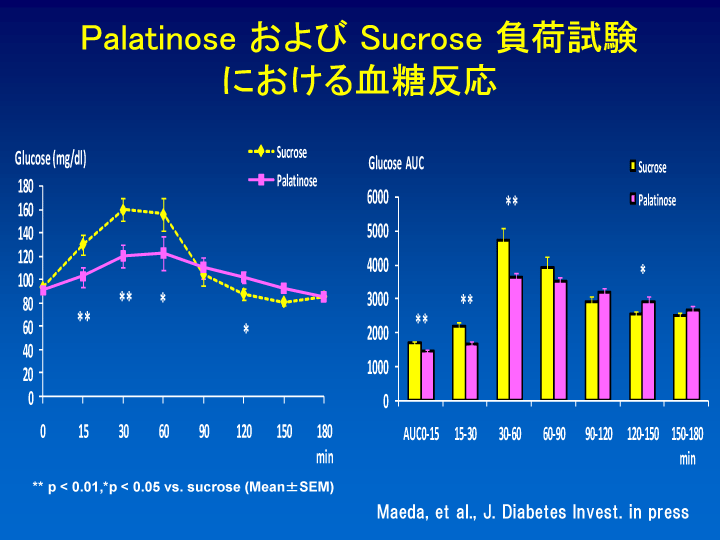
食後の血糖上昇は、なるべく穏やかなほうがいいのです。高濃度のブドウ糖で山が高くなると、血管内皮を傷害するといわれています。こういう高血糖の状態が繰り返し続くことで合併症を引き起こす可能性も高くなります。ですから、急激に血糖値を上げる食品は患者さんにあまり摂ってもらいたくない。
次に、図2を見てください。同じく両糖質摂取後のインスリン分泌量を比較しています。激しく血糖が上がると、膵臓はインスリンを出さざるをえなくなるのです。健常人もしくは軽症の2型糖尿病の人では、まだ膵β細胞が元気なので、上昇した血糖に応じて強く分泌されます。
図2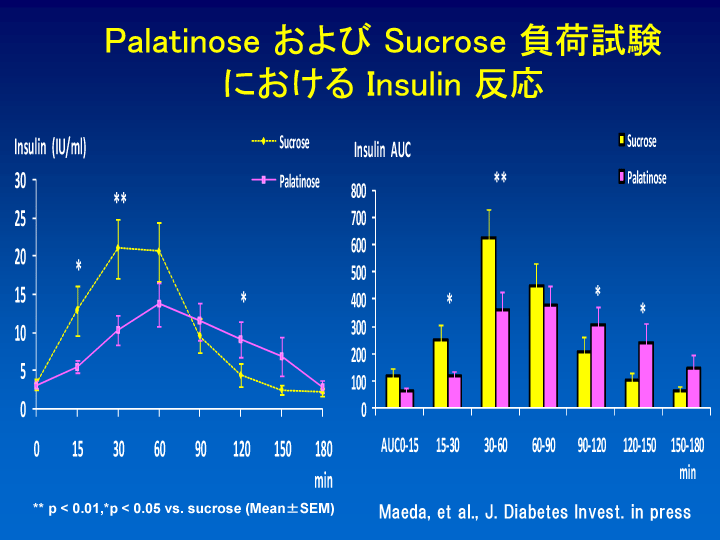
激しくインスリンが出ることによって、血糖値は少し遅れてガクンと下がりこむという現象を引き起こします。ですから、山が高いと、それに巻き込まれて谷も低くなる。急角度に血糖値が下がると、お腹が減ります。
激しい血糖変動が1日に1回でも2回でも繰り返され、年余にわたって継続すれば膵臓にとってはストレスになります。血糖値を急激に上げないということは、長い目でみると合併症の予防のみならず、短・中期的にみれば膵臓の不要なストレスを軽減できる癒やしにもなるわけです。
3. インクレチン(GLP-1とGIP)分泌量を比較
---- 血糖値の上がり方が、パラチノースと砂糖は全然違いましたね。インクレチン分泌も異なる結果だったのですか?
難波: GIP分泌に関しては、僕は頭の中では当然、分解されにくいほう(パラチノース)が刺激しないだろうと予測したのです。そして、分解しやすいほう(お砂糖)は、激しく刺激するだろうと。
そうしたら、その通りでした(図3)。このGIPというホルモンは、腸に栄養が来ましたよ、インスリンを出して、というメッセージを膵臓に伝えるので、出ること自身は悪いことではありません。
図3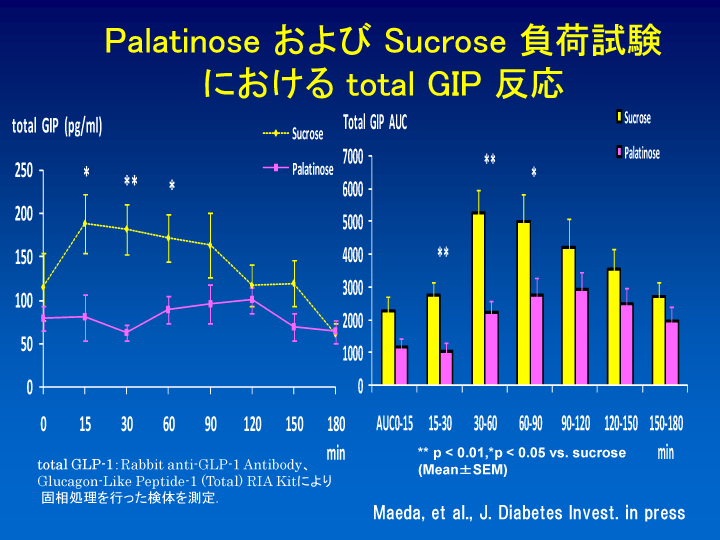
ただし、このホルモンの特徴として、栄養素を脂肪細胞に取り込みやすくさせるという性質があります。ということは、これがあまり激しく出ると、血中の栄養素、ブドウ糖などを脂肪細胞に導入しやすくするので、肥満を助長しやすいと考えられてます。だからGIPは、十二指腸であまりたくさん出過ぎないほうがいい。
そして、さらにもう1つありました。消化吸収されていくと糖はだんだん薄まりながら、下部消化管へ移動します。ここには、GLP-1というホルモンがあります。
GLP-1も、消化管に入った単糖を認識すると消化管粘膜上皮から分泌されます。パラチノースでは分泌されてたGLP-1が、砂糖の場合はすでに上部腸管で消化が終わっているので出ていないことがわかりました(図4)。
図4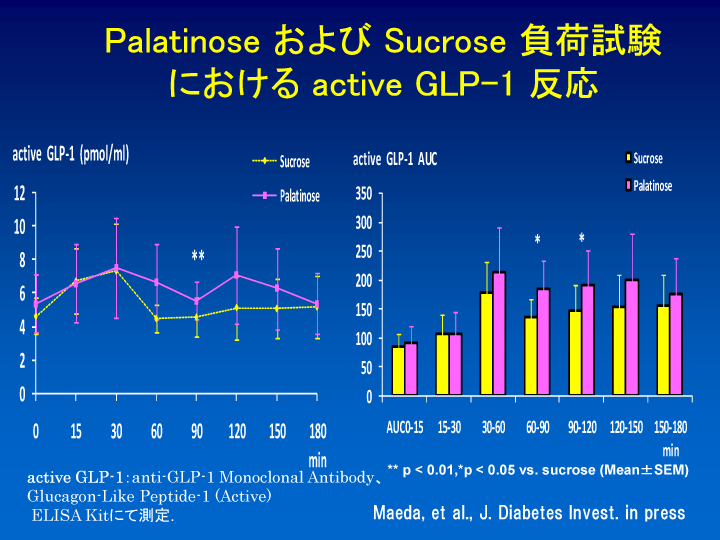
このGLP-1の特徴はGIPの反対で、肥満を抑制しやすい効果を持っており、食欲をブレイクする働きもあります。胃の動きも少しブレイクして食行動を抑えるホルモンが出たほうが、食後の食欲を削ぐ可能性があるわけです。
---- メリットが4つも明らかになったのですね。
難波: とういことで、この研究で生理学的、科学的に証明できる4つの有用性を明らかにすることができました。パラチノースは血管をいじめにくい、膵臓を癒やす、肥満を助長しにくい、そして胃の動きも止めて満腹感を少し強めるのではないか?というものです。
---- 糖尿病治療薬に似た働きがあるのでは?
難波: いやいや、例えばGLP-1受容体作動薬は、これの10倍以上の血中濃度を高めるので桁が違いますよ(笑)。この薬ではその強い作用で胃を止め、食欲を落とそうというもの。パラチノースの場合は、同じような状態をより自然に作り出すということでは似ていますが。ですから、治療というより、予防的レベルのイメージですね。
---- 健常者や血糖値が高めと言われた糖尿病境界型の人には、予防的に使えるのでは?
難波: 健常人や境界型の人では今回の結果からみてシナリオ通りだと思いますが、糖尿病患者さんでどうなのかはわかりません。糖尿病が進むと膵臓が弱ってきて、健常人のようにはインスリンが出にくいはずなので、そういう人でも同じようなメリットが出せるかどうか。まずは、軽症の2型糖尿病患者さんで、研究を行ってみたいです。
4. 今回の研究から「スローカロリー」を考える
---- 今回の研究を見て、「スローカロリー」(ゆっくり消化吸収する)という考え方を、どうお感じになりましたか?
難波: 糖質は、今回の研究のように摂取後の反応で一番シャープに差が出ますからね。スローダイエットというかスローライフというネーミングも聞きますが、同じカロリーでも穏やかに吸収することで、身体にやさしいというコンセプトは着想として間違っていないと思います。
---- 近年、血糖値の上昇を防ぐために、糖質の摂取量を減らす低糖質ダイエットといった考え方が注目されています。一方で、糖質の摂り方として、摂取する糖質の種類を変えてみるという考え方も有効でしょうか。
難波: はい、例えばGI(グリセミックスインデックス)という、食品ごとの血糖上昇に注目した考え方については、海外では山のように文献がありますね。低糖質食という考え方はともかく、スローカロリー食といった考えも1つの食生活の知恵として有用だと思います。
あと、食事の工夫でできることは、野菜を先に食べるというようにプロセスを変えたり、満腹感を変えるということくらいでしょうか。満腹感からすると、糖質をまったく摂らないとむしろ満腹感を得にくいのです。アミノ酸と脂肪だけでは得にくい。だから糖質をある程度摂るということは必要です。だからといってブドウ糖や砂糖のような吸収が早いものは、大量に摂ると身体を痛めつけますよということになります。
---- 健康を維持する食事の方法論は、たくさんありますよね。スローカロリー食でも、食品選びや食べる順番、よく噛むといったこともありますが、どのような食事がよいのでしょうか。
難波: 世にたくさんの料理本があり、身体にいいメニューのレシピもあります。でも、あんな風に毎日支度ができたらいいけどという話ですよね。皆さん、お仕事もっていますから。健康に向けた食生活は、やったほうがいいのは皆、わかっていると思うんです。
5.まとめ
---- では、日常生活で糖質はどのように摂るとよいでしょうか。
難波: いま、コーヒーや紅茶などにお砂糖を入れる人は減っているのではないでしょうか。だから、砂糖なんて摂ってないと思い込んでいる人が多いと思います。でも、実は知らないうちに私たちは砂糖を摂っているんですよね。いわゆる外食とか中食、市販の食品で。なかでも大きいのは清涼飲料水ではないでしょうか。それらには砂糖や液糖(ブドウ糖と果糖)がたくさん使用されています。
ペットボトルの裏を見ると書いてありますが、異性化糖(果糖ぶどう糖液糖)がたくさん使用されています。特に果糖はインスリン抵抗性を助長して、肥満、動脈硬化を促進させることが、様々な研究でわかっています。肥満のある人、食行動の悪い人には、この果糖をよく食べている人が多い。その結果、インスリン抵抗性が強くなって糖尿病になってしまう。果糖の過剰摂取の危険性はもっと認知されるべきだと思います。
吸収が速く、インスリン抵抗性を助長しやすい、糖質を無意識のうちに大量に摂取してしまうことがよくないということで、砂糖を摂ってはいけないというわけではないんですよ。日頃の食生活で、血糖を急激に上げないような、穏やかな食生活の工夫が有用であろうということです。もし、市販の食品や飲料に入れる砂糖や果糖の代わりにパラチノースが使われれば、健康づくりにより有用な可能性があると思います。
6. 研究の概要
天然二糖類イソマルチュロース(パラチノースR)及びスクロースが健常人の血糖および
インクレチン分泌に与える影響
前田亜耶 1、2) 宮川潤一郎 1) 美内雅之 1) 永井悦子 1) 徳田八大 1) 楠 宜樹 1) 村井一樹 1)
勝野朋之 1) 浜口朋也 1) 原納 優 2) 難波光義 1)
1) 兵庫医科大学内科学糖尿病科 2) 児成会生活習慣病センター(ハラノ医院)
【対 象】
- BMI 23以下(21.1±1.6 kg/m2)の健常男性10名
【糖負荷量】
- パラチノース:50g/300 ml、スクロース:50g/300 ml
【測定項目】
- 血糖、インスリン、グルカゴン、インクレチン(total GLP-1、active GLP-1およびtotal GIP)
【目 的】
- パラチノースとスクロースの血糖上昇作用、およびインクレチンホルモン分泌に与える影響を比較検討した。
- また、両糖の味覚に及ぼす影響についても比較した。
【背 景】
- イソマルチュロース(パラチノースR)は、人工的に砂糖のα-1,2結合を転移酵素の作用によりα-1,6結合に作り替えた砂糖の構造異性体であり、自然界で蜂蜜中に微量含まれている。
- 小腸で完全に消化吸収される4 kcal/gの糖質であり、小腸での分解速度が砂糖に比べ約1/5と遅い。また、α-グルコシダーゼの影響を受けにくい。
- パラチノースRの甘味度はスクロースの1/2であるが、甘味の質は、砂糖に非常によく似ている。まろやかでスッキリしていて後味に異味がない。
【まとめ】
- パラチノース液負荷ではスクロース液負荷に比し、
- 血糖値は摂取後15、30、60分において有意に低値を示し、血糖AUC0-60も有意に減少した。また、パラチノース液は60分、スクロース液では30分で頂値あり、スクロース液に比し有意な低値を示した。
- 血中インスリン濃度は摂取後15、30分において有意な低値を示し、インスリンAUC15-60も有意に減少した。
- 血中グルカゴンは摂取前後で両液群間に有意な変化は認めなかった。
- 血中total GIPは摂取後15、30、60分において有意な低値を示し、total-GIP AUC15-90も有意に減少していた。
- 血中total GLP-1及びactive GLP-1は摂取後90分においてのみ有意に増加し、total GLP-1とactive GLP-1のAUC60-120も有意に増加した。
- パラチノース液の味覚に及ぼす影響は、スクロース液に比べて
- 甘さが丁度良い、
- 美味しい、
- 後味が良い
【結 論】
- 糖質の一部をパラチノースに置き換えることで糖質全体の吸収速度が緩やかになり、パラチノースはスクロースに比し食後の血糖上昇を緩やかにすることが可能である。
- パラチノース摂取によって、total GIPの初期分泌が有意に減少し、total GLP-1は後期相で有意に増加することが明らかとなった。
- パラチノースを食事の味付けや甘味料として使用することにより、膵β細胞への負担を軽減しうる可能性がある。
以上より、パラチノースはスクロースに劣らない甘味を有していながら、糖代謝と膵島機能にとっては、より有利な二糖類であると考えられた。
